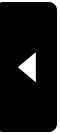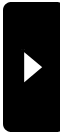2009年02月14日
雪と氷の科学
近畿の山はまだ2月だというのに、雪融けが盛ん。
先日の祝日、山に行く予定なく、近所の図書館に行くことに。
そしてこんなのを借りてきたのでした。

表紙の「雪と氷の科学」という文字に思わず目を惹かれたのでした。
先日の祝日、山に行く予定なく、近所の図書館に行くことに。
そしてこんなのを借りてきたのでした。
表紙の「雪と氷の科学」という文字に思わず目を惹かれたのでした。
雪の結晶といえば、こんなのがまず頭に浮かびますよね。
「樹枝状結晶」です。

時にはこんなのも。 「扇形結晶」です。

でも、様々な気象条件によりこんな形状の結晶もあります。
気温が高い時にはこんな結晶が出来ます。
「針状結晶」です。

気温が低く、大気中の水蒸気量が少ない時には、こんな結晶も。
「角柱結晶」です。

アメリカのアマチュア研究家、ウィルソン・ベントレーが1931年に雪の結晶の
写真集を世界で初めて発表しました。
そのベントレーに魅了されたのが日本の物理学者・中谷宇吉郎であります。
ベントレーのような結晶写真の撮影を試みた彼は、
「実験室でその美しさを再現できないか?」と考えるようになり、
3年の研究ののち、1936年、世界で初めて雪結晶をつくることに
成功したのでした。
さらに研究を進めた彼は、実験装置内の湿度と温度を変え、様々な形の
人工雪の結晶を作り出したのでした。
そして、そこから「雪の結晶の形を見れば、上空の湿度と気温を知ることができる。」
ということを研究成果としてあげたのでした。
雪の結晶は千差万別であり、観察は一瞬の勝負であるそうです。
その時間はわずか15秒ほど。
雪の結晶は顕微鏡に載せると、照明の熱や観察者の体温をうけて
みるみるうちに融けだすのだという。
また、雪の結晶はすべて六角形が基本となっているそうです。
このなぞは分子の並び方にあるそうです。
しかし、このへんの話は難しすぎる・・・・のでパス。
春一番が吹き荒れた日本列島。春が一歩近づいた感がありますが、
まだもう少し、雪の世界を楽しみたい今日この頃であります。

「樹枝状結晶」です。

時にはこんなのも。 「扇形結晶」です。

でも、様々な気象条件によりこんな形状の結晶もあります。
気温が高い時にはこんな結晶が出来ます。
「針状結晶」です。

気温が低く、大気中の水蒸気量が少ない時には、こんな結晶も。
「角柱結晶」です。

アメリカのアマチュア研究家、ウィルソン・ベントレーが1931年に雪の結晶の
写真集を世界で初めて発表しました。
そのベントレーに魅了されたのが日本の物理学者・中谷宇吉郎であります。
ベントレーのような結晶写真の撮影を試みた彼は、
「実験室でその美しさを再現できないか?」と考えるようになり、
3年の研究ののち、1936年、世界で初めて雪結晶をつくることに
成功したのでした。
さらに研究を進めた彼は、実験装置内の湿度と温度を変え、様々な形の
人工雪の結晶を作り出したのでした。
そして、そこから「雪の結晶の形を見れば、上空の湿度と気温を知ることができる。」
ということを研究成果としてあげたのでした。
雪の結晶は千差万別であり、観察は一瞬の勝負であるそうです。
その時間はわずか15秒ほど。
雪の結晶は顕微鏡に載せると、照明の熱や観察者の体温をうけて
みるみるうちに融けだすのだという。
また、雪の結晶はすべて六角形が基本となっているそうです。
このなぞは分子の並び方にあるそうです。
しかし、このへんの話は難しすぎる・・・・のでパス。
春一番が吹き荒れた日本列島。春が一歩近づいた感がありますが、
まだもう少し、雪の世界を楽しみたい今日この頃であります。
Posted by tekapo at 22:55│Comments(10)
│徒然なるまま
この記事へのコメント
雪もいろいろあって面白いですね。
でもやっぱり本物が見たーい!
来週末はいい感じになりそうですね。
やっとわたしも雪中カヌーキャンプにいけるかな?
でもやっぱり本物が見たーい!
来週末はいい感じになりそうですね。
やっとわたしも雪中カヌーキャンプにいけるかな?
Posted by フジタLG-2 at 2009年02月14日 23:12
まず・・こんな本も借りれる事にビックリ・・
私の町では・・借りれません(*--)
でも突き詰めていくと、面白い研究のようですね~興味津々!
私の町では・・借りれません(*--)
でも突き詰めていくと、面白い研究のようですね~興味津々!
Posted by fuji-sin at 2009年02月15日 05:26
北海道にも実験室で雪の結晶を人工的に作って研究している先生がおられますね。
興味本位で見ているだけなんで楽しそーです^^;
来週からはちょっと降ってくれそうですね。
週末には楽しい雪山が迎えてくれることを期待して・・・
興味本位で見ているだけなんで楽しそーです^^;
来週からはちょっと降ってくれそうですね。
週末には楽しい雪山が迎えてくれることを期待して・・・
Posted by tetsu at 2009年02月15日 12:09
フジタLG-2さん 今日は~
明日からの雪はどんな結晶の雪なんでしょう。
いい雪を期待したいですねぇ~
明日からの雪はどんな結晶の雪なんでしょう。
いい雪を期待したいですねぇ~
Posted by tekapo at 2009年02月15日 18:50
fuji-sinさん 今日は~
Newtonの他にも岳人、BE-PALなどもあり、
貸出しもできるのでありがたいです。
Newtonは自然遺産などの紹介もよく載っているので
以前はよく買っていました。最近は・・・・ 借りることが多いかな。
雪の結晶って、スキー場のリフト乗車中に、
ウェアに舞い降りてきたのを観察したりしますが、
結晶の科学を追及するとこんなにも奥が深いのですね。
Newtonの他にも岳人、BE-PALなどもあり、
貸出しもできるのでありがたいです。
Newtonは自然遺産などの紹介もよく載っているので
以前はよく買っていました。最近は・・・・ 借りることが多いかな。
雪の結晶って、スキー場のリフト乗車中に、
ウェアに舞い降りてきたのを観察したりしますが、
結晶の科学を追及するとこんなにも奥が深いのですね。
Posted by tekapo at 2009年02月15日 18:56
tetsuさん 今日は~
明日からの寒の戻りに期待したいですね。
今週末は芦生行けそうかな~
明日からの寒の戻りに期待したいですね。
今週末は芦生行けそうかな~
Posted by tekapo at 2009年02月15日 18:57
きれいですね~。
これって、コンパスについてるルーペとかで、見れるもんなんでしょうか?
これって、コンパスについてるルーペとかで、見れるもんなんでしょうか?
Posted by ibex at 2009年02月15日 20:41
こんばんは~~。
私は元々、寒いのが苦手で、雪にはあまり親しみがないのですが・・・
(ホント、つい最近なんですよ、雪遊びを始めたのはww)
中谷宇吉郎さんは聞いたことあります!
この有名な言葉で~~
↓
「雪は天から送られた手紙である」
・・・こんな素敵な言葉も、ご自分の研究をしっかりやってはったからこそ、言えるのでしょうね~~。
物理学者でありながら、文学者でもあり・・・ロマンチックですよねぇ~~。
私は理系はトンとダメなので、ホンマすごいと思います(^ω^)/
私は元々、寒いのが苦手で、雪にはあまり親しみがないのですが・・・
(ホント、つい最近なんですよ、雪遊びを始めたのはww)
中谷宇吉郎さんは聞いたことあります!
この有名な言葉で~~
↓
「雪は天から送られた手紙である」
・・・こんな素敵な言葉も、ご自分の研究をしっかりやってはったからこそ、言えるのでしょうね~~。
物理学者でありながら、文学者でもあり・・・ロマンチックですよねぇ~~。
私は理系はトンとダメなので、ホンマすごいと思います(^ω^)/
Posted by さなまる at 2009年02月15日 21:46
ibexさん 今晩は~
樹枝状結晶なら条件さえそろえば10ミリ近くにまで
成長するそうです。
そうか、シルバコンバスなんかについているルーペで
観察するという手がありますね。
樹枝状結晶なら条件さえそろえば10ミリ近くにまで
成長するそうです。
そうか、シルバコンバスなんかについているルーペで
観察するという手がありますね。
Posted by tekapo at 2009年02月15日 21:53
さなまるサン 今晩は~
中谷宇吉郎さんの「雪は天から送られた手紙である」
の言葉はすなわち
「雪の結晶の形を見れば、上空の湿度と気温を知ることができる。」
の言い換えなのですよね。
雪山で、青空が除いているのに風に運ばれてヒラヒラと
舞い降りる雪の結晶。
そんな時は結晶の形に見とれてしまいます。
中谷宇吉郎さんの「雪は天から送られた手紙である」
の言葉はすなわち
「雪の結晶の形を見れば、上空の湿度と気温を知ることができる。」
の言い換えなのですよね。
雪山で、青空が除いているのに風に運ばれてヒラヒラと
舞い降りる雪の結晶。
そんな時は結晶の形に見とれてしまいます。
Posted by tekapo at 2009年02月15日 21:58
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。